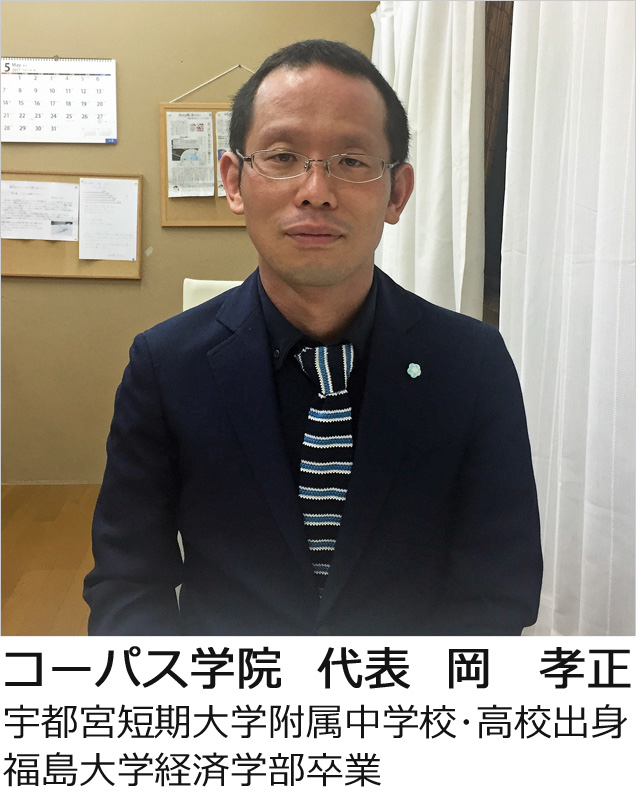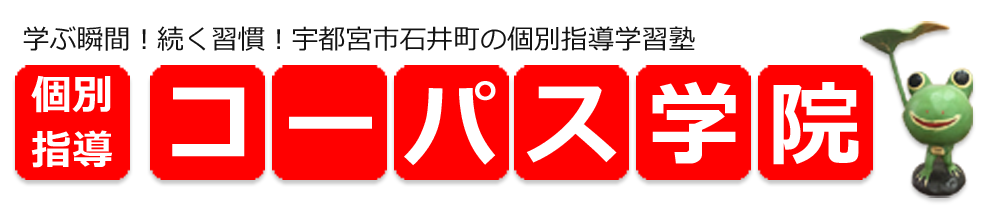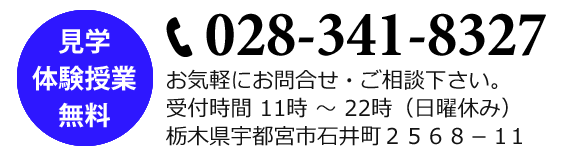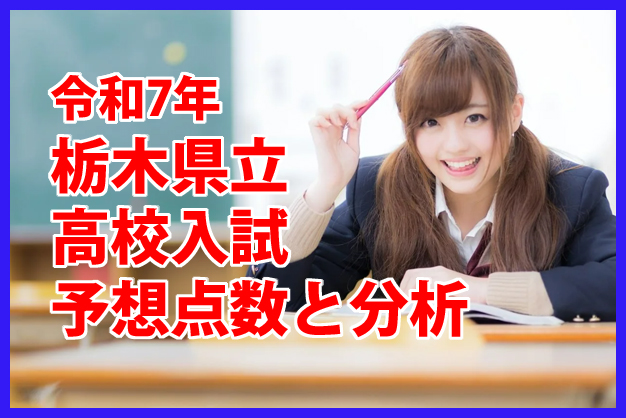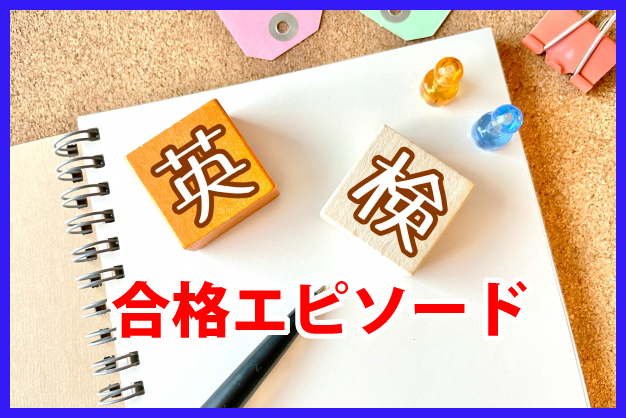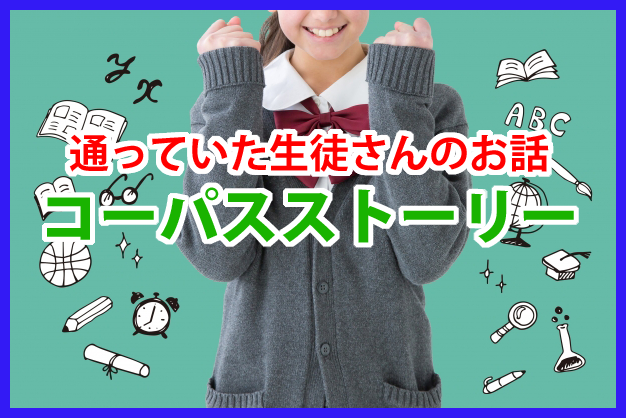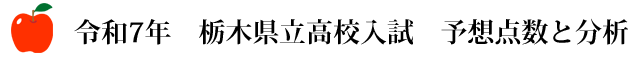
令和7(2025)年度県立高等学校入学者選抜の結果について
令和7(2025)年度県立高等学校入学者選抜の結果について、栃木県のホームページ(https://www.pref.tochigi.lg.jp/m04/r07/documents/20250516112646.pdf)に掲載されています。
ここでは、その集計をもとに予想点数を示そうと思います。また、各教科ごとに正答してほしい問題、無理に解かなくてもいい問題に分けて解説したいと思います。
正答してほしい問題は、なるべく点数を落としてほしくないところです。
また無理に解かなくてもいい問題は、時間的にも余裕があれば挑戦すべきで、難易度が高いことが多いです。
後で解こうとしていた問題があれば、そこに時間を使った方が点数を稼げます。
では早速5教科の合計点数からお伝えします。令和7年栃木県立高校入試の予想点数は、256.9点です。各教科ごとでは、国語(60.6点)、社会(57点)、数学(40.3点)、理科(52.4点)、英語(46.6点)と予想します。
ここからは、各教科ごとに具体的に解説します。
国語
まず国語からです。大問1は、漢字の正しい読み方と書き方です。
読み方で最も正答率が低かったのは「添削」です。書き方で最も正答率が低かったのは「ガイロ樹」です。
大問1で言えることは、読み方よりも書き方の方が、全体として正答率が低いことです。
書き方で9割を超えた正答率は一つもありませんでした。
一方で、読み方で9割を超えたのは3問ありました。
大問2は説明的文章です。
2つの文章を読んで、それぞれについて答えさせたり、2つの文章に共通する内容を選ばせたりする問題です。
指定された単語を用いて60字以内で答えさせる問題は、部分正答も含めて4割ほどです。
解かずに時間が余ったとき、もう一度考えてもいいと思います。
大問3は文学的文章です。
説明的文章でもそうだったように、50字以内と55字以内で答えさせる問題は、部分正答を含めてそれぞれ7割以下、6割ほどです。
本文の表現がどのような効果を生んだかを記号で選ばせる問題は、7割の正答率です。
大問3の1と2の正答率が8割以上だったのと比べると低いです。
大問4は古文です。
現代語訳をさせて15字以内で答えさせる問題は、部分正答も含めて3割です。
どこを訳せばいいのだろうと難しく感じたら、後回しにしましょう。
短歌の掛詞を答えさせる問題は、正答率が2割です。
「くらひ」を「食らひ」と掛けているもう一つは何か。
「くらい」つまり「位」が思いつくかです。
大問5は会話文の中で使われる漢字や文法などを答えさせる問題です。
動詞の活用形を答えさせる問題の正答率は5割以下です。
表から読み取れることを記号で選ばせる問題も5割以下です。
選択肢の文章のどれが間違っているのかを考えなければならず、解くのに慣れていないと結構時間がかかります。
社会
次の科目は社会です。社会の問題の特徴としては各大問に、文章で答えさせるのが一問ずつあることです。
配点は4点です。
二つの文章のうち、一つが正しく書ければ2点、もう一つ正しく書ければもう2点加えて4点です。
2点でも取れたらいいな、くらいのつもりでいいと思います。
大問1は小問集合です。
貨物輸送量の輸送機関別割合を答えさせる問題の正答率が5割以下です。
教科書には棒グラフで年代ごとの推移も載っています。
試験問題には数値だけが表になっていたので、そこから読みとるのが難しかったのかもしれ
ません。
大問2は世界全体の地理に関して答えさせる問題です。
表の数値からどの国なのかを選ばせる問題の正答率は4割以下です。
大問1と同じように、表にあるのは割合の数字だけなので、迷ったかもしれません。
地理的な近さを意識できれば、解くことができます。
大問3は古代から近世にかけての日本の歴史に関する問題です。
「保元の乱」と答えさせる問題の正答率が3割以下です。
文章内に「平治の乱」と並んでいるのがヒントです。
文章の後半で「源頼朝」と答えさせる問題の正答率は5割以下です。
それほど難しくない用語も「平氏を倒して・・・」とあると、答えにくかったかも
しれません。漢字の間違いもあるでしょう。
大問4は近代以降の日本の歴史に関する問題です。
「与謝野晶子」と答えさせる問題の正答率が4割以下です。
またどの出来事がどの時代にあったのか、選ばせる問題の正答率が3割です。
これはよく出題されますが、解くのが難しいです。
特に昭和時代は数年単位で整理しなければならいので、大変です。
大問5は日本の公民に関する問題です。
「公共の福祉」と答えさせる問題の正答率が4割です。
また裁判員裁判について、それぞれの文章が正しいか間違えかを選ばせる問題の正答率も4割です。
大問6は世界を含めた公民に関する問題です。
「主権」と答えさせる問題の正答率は3割です。
国家の要素として覚えておくのは、難しいです。
公民は、地理や歴史と違って、日常でも使われる用語を覚えなければならないので、用語として頭で整理するのが難しいです。
数学
次の科目は数学です。大問1は小問集合です。
二つの一次関数の傾きと切片の大小を選ばせる問題の正答率は4割です。
どちらも傾きがマイナスなので、大小を勘違いしたかもしれません。
データの四分位範囲を計算させる問題の正答率は5割ほどです。
引き算をするだけなので、四分位範囲の意味を忘れてしまったかもしれません。
大問2は平方根、連立方程式の利用、文字式の利用に関する3問です。
正答率は順番に、6割、5割、4割ほどです。
部分正答も含めると、それぞれ1割ほど増えます。
普段の勉強でも途中の式を消さずに、なるべくノートに残しておくと正しく答えられるようになります。
大問3は作図、体積、四角錐の高さ、図形の相似証明に関する問題です。
2つに分けられた四角錐の体積比を答えさせる問題の正答率は、3割以下です。
面積比から辺の比を計算するのが難しいかもしれません。
次の四角錐の高さを答えさせる問題は、前の答えが分かっていないと解けないので、さらに正答率は下がります。
この2問は時間がかかるので、後回しにしていいかもしれません。
大問4はデータの比較から3問、確率の1問の合計4問です。
最近はデータに関する問題は特に増えています。
表から読み取れることを、文章で答えさえる問題の正答率は5割ほどです。
確率の正答率は3割です。
定期テストでもよく出題されるサイコロの目の和についてです。
前置きの説明を理解するのに、時間がかかったかもしれません。
大問5は関数の6問です。
関数は中学三年間で学ぶ中で、どの単元よりも難しいです。
関数は範囲が広く、復習するのに時間がかかります。
変化の割合についての正答率は2割以下です。
二次関数と反比例のグラフが混ざった問題は珍しいです。
他に2%や1%以下の正答率の問題もあります。
実際に解くときは、飛ばしてしまいましょう。
大問6は規則性に関する問題です。
3問あって正答率は順番に3割、2割以下、部分正答を入れて1割です。
時間に余裕がないと難しいです。
最初の説明を読んで内容を理解するのにも、時間がかかります。
制限時間の残りが10分以下であれば、大問6を解こうとせずに、他の解けなかった問題に取り組んだ方がいいです。
理科
次の科目は理科です。大問1は中学3年の生物の連続性からの問題です。
染色体の本数を、それぞれの成長の過程において答えさせる問題の正答率は、3割以下です。
部分正答も含めて6割以上です。
胚の染色体の本数が迷ったかもしれません。
大問2は中学1年の光による現象からの問題です。
凸レンズを使った実験で、物体の位置を答えさせる問題の正答率は2割以下です。
方眼紙に書いて答えさせるので、特に難しいと思います。
目のつくりと関連させて、像を作るしくみを記号で選ばせる問題の正答率は3割以下です。
部分正答も含めて8割以下です。
大問3は中学1年のゆれる大地からの問題です。
S波が到達するまでの時間を答えさせる問題の正答率は2割ほどです。
グラフを書くと解きやすいですが、時間を計算するなどして考えるので、慣れていないと難しいかもしれません。
大問4は中学3年の化学変化とイオンからの問題です。
水が生じる化学変化の式を答えさせる問題の正答率は4割です。
イオンを使って書くので、化学反応式だと勘違いしてしまったかもしれません。
大問5は中学2年の電流と磁界からの問題です。
誘導電流の流れる向きと大きさを、記号で選ばせる問題の正答率はどちらも4割です。
計算で解く問題ではないのですが、論理的に考える必要があってどちらも難しいと思います。
大問6は中学2年の動物の体のつくりとはたらきからの問題です。
体循環と肺循環を合わせた血液の流れる順番を、記号で答えさせる問題の正答率は3割以下です。
それぞれの用語の意味を知ってる上で、それらを適切に並び替えなければいけないので、難しいと思います。
大問7は中学1年の物質のすがたとその変化からの問題です。
沸点に達してからのエタノールの状態と、エタノールの体積を変えたときの沸点の変化を、記号で選ばせる問題の正答率は2割ほどです。
沸点に達すると、液体は全て気体になると勘違いしたかもしれません。
どちらか片方の正答率が6割ほどです。
大問8は中学3年の太陽と恒星の動きからの問題です。
日周運動と年周運動を組み合わせて星の位置を、記号で選ばせる問題の正答率は3割です。
日周運動は1時間15°、年周運動は1日1°を使って、それぞれ計算して星の位置を想像するので難しいかもしれません。
英語
次の科目は英語です。大問1はリスニング問題です。
対話を聞いて記号を選ばせる問題の正答率は2割ほどです。
質問と答えた内容をそれぞれ聞き取らなければいけないので、難しいかもしれません。
大問2は文法を中心に適した語を選んだり、並び替えさせたり、5文程度の英文を書かせたりする問題です。
文頭で逆説の接続詞を選ばせる問題の正答率が1割ほどです。But(=しかし)を選んでしまった人が多かったのかもしれません。
現在分詞を使って並び替えする問題の正答率は4割以下です。
大問3は英文を読んでその内容を答えさせる問題です。
答えとなる英文を探して、日本語訳をさせる問題が2つあり、正答率は部分正答を含めてそれぞれ7割以下、3割ほどです。
下線部の直前にある2つの英文を訳すので、簡単に探すことはできても、単語や文のつながりで訳すことが難しいかもしれません。
大問4も英文を読んでその内容を答えさせる問題です。
大問3より英文は長くなっています。
本文から6語で抜き出して答えさせる問題の正答率は、2割ほどです。
下線部から少し離れたところに答えがあるので、探すのが難しいです。
大問5は二人の対話文からその内容を答えさせたり、グラフに入る記号を選ばせたりする問題です。
絵や日本語から英文を書かせる問題の正答率は部分正答を含めて、それぞれ2割、3割ほどです。
英文を書かせる問題は難しいので、無理に解こうとせず後回しにしてもいいです。
また、対話の中の出来事について、年代順に並び替えさせる問題の正答率は1割ほどです。
全て正しく並び替えなければならず、そのための時間を考えると、これも後回しにしていいと思います。
令和5年栃木県立高校 入試問題 平均点と分析はこちら


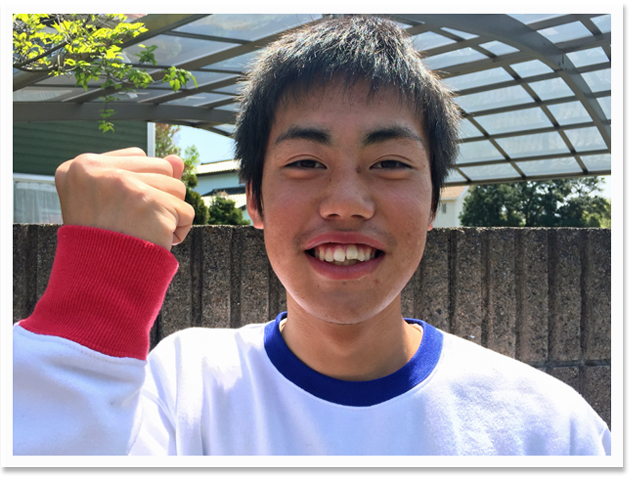
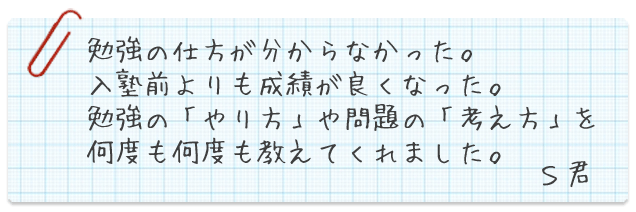
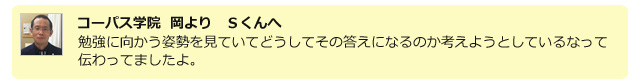
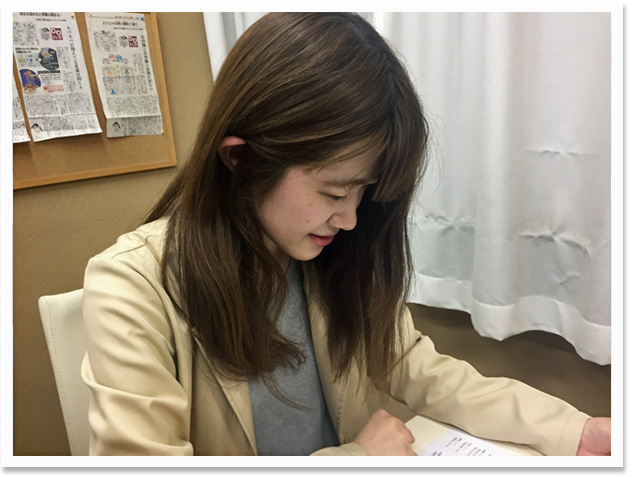
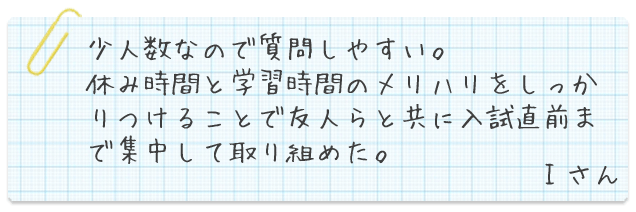
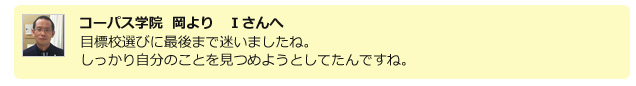
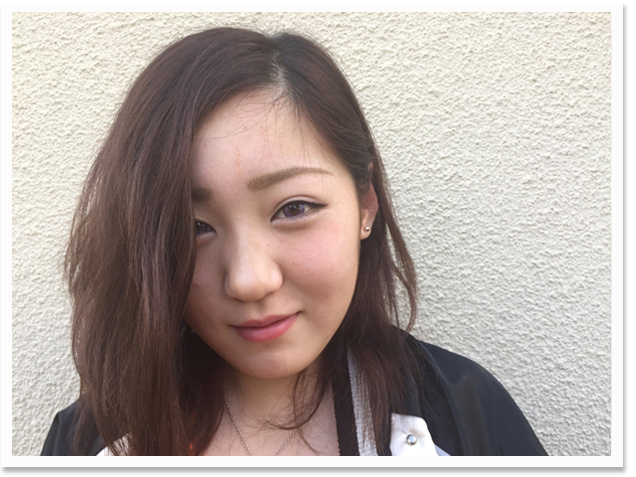
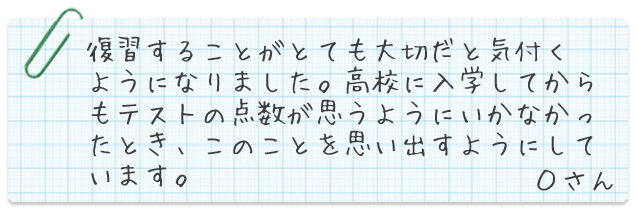
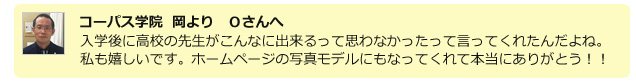
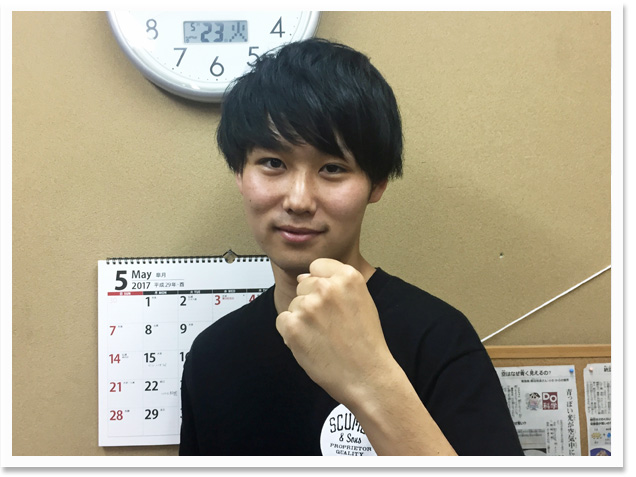
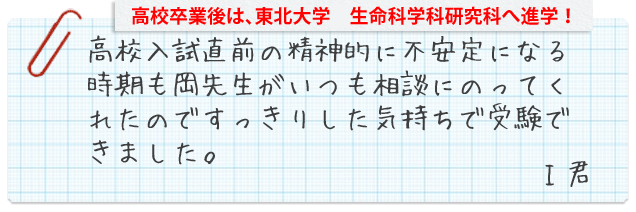
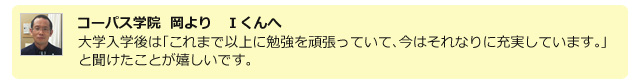
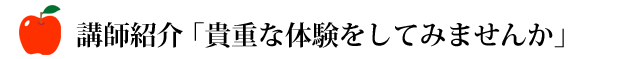
私は浪人して大学に行きました。
それから就職を何度か繰り返してきて、これまでの人生はずいぶん遠回りしているかもしれません。しかしその分「回り道」をしたことでどんな経験も無駄ではなかったとも思っています。
人生の中で受験は通過点の一つに過ぎませんが、大きな試練の一つでもあります。子供から大人へと成長しようと「脱皮」している彼らに手助けしてあげたいと考えています。
ぜひ一度ご連絡ください。
彼らの力になるべくご相談、ご質問等お待ちしています。
それから就職を何度か繰り返してきて、これまでの人生はずいぶん遠回りしているかもしれません。しかしその分「回り道」をしたことでどんな経験も無駄ではなかったとも思っています。
人生の中で受験は通過点の一つに過ぎませんが、大きな試練の一つでもあります。子供から大人へと成長しようと「脱皮」している彼らに手助けしてあげたいと考えています。
ぜひ一度ご連絡ください。
彼らの力になるべくご相談、ご質問等お待ちしています。